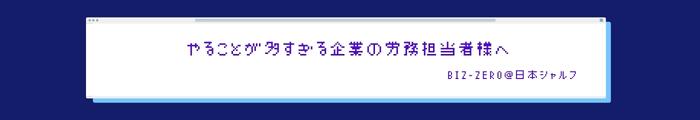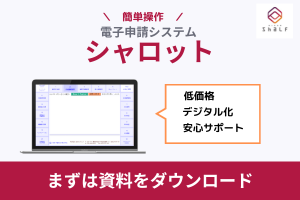【民法改正】成人年齢の引き下げ、人事・労務担当者が気をつけるべきことは?

はじめに
2022年4月1日より、成人年齢(以下、成年)が20歳から18歳へ引き下げられます。140年にわたり明治時代から維持されてきた成年20歳の変更には、約343の法令・規則等の見直しが生じたようで、制度的な問題にとどまらず、人々の習慣や価値観をも含めた、社会の隅々に影響を及ぼすことは想像に難くありません。特に、生活に重大な影響を及ぼす事項は所管官公庁等からQ&A等の案内が多く出されております。
そんな中で、今回は、成年に関する基本的、原理的な考え方を抑えつつ、人事・労務担当者にとって関係しそうな事項について、紹介していきます。また、この機会に改めて、未成年者の取り扱いについて再確認をし、成年の引き下げによって、「変わるもの」「変わらないもの」を整理し、2022年4月に備えましょう。
そもそも成年とは?
「成年」とは、「人が完全な行為能力を有するとみなされる年齢」を意味します。
「完全な行為能力を有する」というのは、「私法上」の契約等の法律行為を「単独で有効」に行えることを指します。成年に達していない者は「未成年者」となり、完全な行為能力を有しません。完全な行為能力を有しない者は「制限行為能力者」と呼ばれます。
➀「みなされる」、➁「単独で有効」、③「私法上」のキーワードで見ていきましょう。
➀「みなされる」
年齢によって「一律」に、成人と未成年者を区別することになります。実際には、未成年者だが大人びている方や成人なのに子供みたいな方がいるかもしれませんが、そういった具体的な事情を考慮せずに、「年齢で一律」に決まることになります。
年齢に基づき未成年者に該当する者に対して、一律的な制限を行い、かつ成人とは異なった保護をはかっているのが特徴となります。この年齢について、何歳が正しいかは一義的に決まっておらず、各国の立法政策で、妥当と考えられている年齢が設定されております。
➁「単独で有効」
自身の法律行為を自身で完結することができる、という意味になります。ここでは、完全な行為能力を有しない「制限行為能力者」を挙げて、説明していきます。
「制限行為能力者」には、「未成年者」の他に、「成年被後見人」、「被保佐人」、「被補助人」の4類型があります。例えば、「被保佐人」というのは、保佐「される」人という意味で、保佐「する」人が「保佐人」となります。
「成年被後見人」とは、『精神上の障害により、判断能力を「欠く常況」にある者』で、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者で、監督者として「成年後見人」が選任されます。「成年後見人」は代理権、取消権を用いて、監督します。
「被保佐人」とは、『精神上の障害により、判断能力が「著しく不十分」である者』で、家庭裁判所により保佐開始の審判を受けた者で、監督者として「保佐人」が選任されます。「保佐人」は代理権、取消権、同意権、追認権を用いて、監督します。
「被補助人」とは、『精神上の障害により、判断能力が「不十分」である者』で、家庭裁判所により補助開始の審判を受けた者で、監督者として「補助人」が選任されます。「補助人」は代理権、取消権、同意権、追認権を用いて、監督します。
・代理権
包括的または一定の範囲内で、制限行為能力者に「代わって」行為を行う権限
・同意権
「事前に同意を与えて」、制限行為能力者の行為を有効にする権限
・取消権
同意を得ずに行った制限行為能力者の行為を、「取り消す」権限
・追認権
「事後に同意を与えて」、制限行為能力者の行為を有効にする権限
他方、完全な行為能力を有する者は、上記のような代理権、取消権、同意権、追認権に服しません(そもそも法的に監督する者はいません)。すなわち、単独かつ有効に法律行為を行うことができます。
「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」となるには、「判断能力」に関する実体的要件と「家庭裁判所の審判」という手続的要件を満たさなければなりません。年齢によって一律に判断される「未成年者」との違いが浮き彫りになったと思います。
③「私法上」
「私法」とは、社会生活に関する法律の総称で、私人間に関するルールを定めています。対するものに「公法」があり、憲法や行政法といった、私人対公権力(国家、地方公共団体など)、公権力間に関するルールを定めています。全ての法律が「私法」と「公法」のどちらかに単純に分類できるわけではありませんが、「私法」とは社会生活上の私人間のルールを定めている法律だというイメージを持っていただければと思います。
私法の代表格は「民法」であり、契約等(財産)や親族等(家族)に関する基本的なルールを定めております。
未成年者に関する「現行」民法の規定
現行の成年が20歳である根拠は、民法第4条「年齢二十歳をもって、成年とする」となります。
20歳未満の未成年者に関する規定として、第5条1項本文「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」、第818条1項「成年に達しない子は、父母の親権に服する」、第838条1号「後見は、・・未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき・・に開始する」が挙げられます。
未成年者は、単独で有効な法律行為ができず、法定代理人の同意が必要となります。法定代理人とは親権者や未成年後見人を指し、例えば、親権者たる親が法定代理人となります。
このように、成人と未成年者の法的に大きな違いは、「単独で有効に法律行為ができるか」「親権に服するか」、ということになります。なお、未成年者が同意を得ずに行った法律行為の効果は即座に無効というわけではなく、親権者によって取り消される(取消権が行使される)可能性があり、そういう意味で不安定な状態にある(単独で有効にできない)、ということになります。
ただし、(一定の年齢以上の)未成年者の場合、単独で有効にできる行為があります。例を挙げていきますと、
➀未成年者に損害を及ぼすおそれがない行為
第5条1項のただし書きには「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない」とあります。
➁法定代理人が処分を許した財産の処分
第5条3項では「・・法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする」とあります。
目的を定めないで処分を許した財産とは、例えば「お小遣い」が挙げられます。
③許可された営業の範囲内の行為
第6条1項では「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」とあり、ある営業を許された未成年者をその営業の範囲内で、成人と同等に扱うことを認めた規定となります。
営業活動では、ときには迅速な判断が必要となる場合があり、また、取引の相手方(そのまた取引の相手方そのまた・・)が存在するのが普通です。もし、このような場面でも、法定代理人の同意が必要となると、迅速な判断や行動ができません。加えて、相手方からすると、取引がいつか取り消されるという不安にさらされます。そういった懸念を払拭するために、未成年者でも「営業の範囲内で」成人と同等に扱うことを認めております。
④「養子」となる縁組を承諾する行為
第797条では「養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる」とあります。15歳以上であれば未成年者であっても、法定代理人を介さずに、単独で有効に承諾をすることができます。
⑤遺言をする行為
第961条では「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」とあります。
上記➀➁③は、財産・取引関係上のルールとなります。未成年者の行為には相手方や第三者がおり、その方々の保護(取引の安全)と未成年者の保護を調整する規定となります。
上記④⑤は、家族・身分に関するルールであり、こちらは取引の安全というよりも、事柄の性質上、未成年者本人の意思を尊重することに重点がおかれ、15歳以上という比較的低年齢の未成年者が単独で有効にできることを民法が認めております。
以上➀~⑤の事項は、具体的、限定的な規定となりますが、より包括的な規定・制度があります。それは「婚姻による成年擬制」となります。
⑥婚姻による成年擬制
第753条「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす」と、第731条「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない」の規定により、婚姻をした場合は、男性では早くて18歳、女性では16歳から成人とみなされます。ただし、第737条によって、未成年者の婚姻には、父母(またはその一方)の同意が必要となります。婚姻(成年擬制)に至るまでは、成人とは異なった制限(保護)が見受けられます。
なお、婚姻可能年齢については、(成年の引き下げと同じタイミングの)2022年4月1日から変更があります。すなわち、女性の年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳に統一されることになります。
「成年擬制」とは、婚姻した未成年者を、私法上の成人とみなして、単独で有効に契約等の法律行為ができるようにする制度となります。そのため、17歳の未成年者が婚姻をしても、飲酒や喫煙ができるわけではありません。これは飲酒や喫煙を禁止している法律の目的・趣旨と成年擬制の目的・趣旨が異なることによるものです。
他の法律に目を向けると、法律行為ではありませんが、参考までに、現行の未成年者が成人と同様にできる行為を挙げていきます。
⑦選挙や憲法改正の投票権(公職選挙法、国民投票法)
18歳以上であれば、未成年者でも投票ができます。
⑧バイクや自動車の免許取得(道路交通法)
バイク免許(大型二輪免許を除く)は16歳以上、自動車免許(大型二輪免許を含む)は18歳以上の未成年者でも取得ができます。
⑦⑧は、私法上の問題ではなく、各々の法律で、その目的に沿って、行為ができる年齢を定めており、成年擬制は関係ありません。
人事・労務分野の未成年者
ここでは、人事・労務担当者にとって関係しそうな、労働基準法、社会保険法、税法(年末調整関係)の各分野における未成年者の取り扱いについて、みていきましょう。
◆労働基準法
労働基準法(以下、労基法)は、20歳未満の未成年者を、さらに段階を設けて(未熟さに応じて)、就業できる業務や時間等を制限して、未成年者の保護をはかっているのが特徴となります。
キーとなる年齢は、20歳、18歳、16歳(男性)、15歳、13歳となります。では、具体的にみていきましょう。
➀未成年者(18歳以上20歳未満)
労基法上、18歳以上の者に就業制限はありません。20歳以上の成人と同じ業務や深夜労働を行わせることができます。
(未成年者の契約)
第58条1項には「親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない」とあり、民法第5条1項本文では「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」とあります。
親権者が、未成年者を「代理」して、法律行為となる労働契約を締結することは禁止されていますが、未成年者が締結する労働契約には親権者の「同意」が必要となります。「代理」と「同意」が異なる行為であることに注意をしましょう。
未成年者との契約締結後、親権者による同意がないことによって発生する問題やリスクを回避するために、同意があることを証する同意書(を兼ねた書類)を求める会社もあります。
(未成年者の契約の解除)
第58条2項では「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる」とあります。未成年者の労働契約に親権者が同意していたとしても、未成年者を保護するために、不利な場合には、労働契約を将来に向かって解除することを認めた規定となります。
(未成年者の賃金請求)
第59条では「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない」とあります。
さらに、会社が賃金を「直接」社員に支払うことを要求している、第24条本文「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」が、ここでは関係してきます。第59条に違反した場合は法定代理人(親権者、後見人)に、第24条違反の場合は使用者に、それぞれ罰則が適用されるので、会社としても注意が必要となります。
上記第58条1項と第59条は、親が子の意向を無視して働かせたり、子が働いたことに対する賃金を親が搾取していた、という歴史的な背景を踏まえて、親から子を守る、親の搾取を防止する、そういう趣旨で定められました。もちろん、現実として、すべての親がそうとは限りませんが、「民法」では親は法定代理人として子を保護する存在、他方「労基法(労働法)」だと、親は子を(多少なりとも)害する存在と捉え、両者では相反する親の捉え方が条文に反映されているようです。
なお、第59条2項では、子に不利な場合、親は子のために将来に向かって労働契約を解除できることを認めており、民法と同様、親が子を保護する存在であるようにみえます。ただし、子のために解除できる者が親に限らず、「行政官庁」も含まれております。見方をかえると、親だけでは子の保護に不十分、ひいては親は信用できないというニュアンスもみてとれます。
(未成年者の職業訓練生の年次有給休暇)
第72条に「第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と・・する」とあります。
職業能力開発促進法の認定を受けて、特例の職業訓練を受けている未成年者に対して、最低「12労働日」の年次有休を付与しなければならないことを規定しております。
成人であれば、最低が「10労働日」であることと比べると、未成年者の職業訓練生に対して手厚い保護がされております。
こちらは、行政通達(昭和22年12月9日基発53号)によれば、「法第70条及び第71条の規定の適用を受ける労働者は、ある種の労働条件について一般労働者より不利なる取扱を受けることとなるため、特にその未成年者に対しては、年次有給休暇については一般労働者より高い基準によって取扱う」という趣旨に基づくものとなります。
➁年少者(18歳未満)
労基法は18歳未満を「年少者」とし、18歳以上の者とは異なった特別な保護をはかっております。関係条文は以下の通りとなります。
(時間外労働、休日労働の制限)
第60条(第32条、第36条)により、年少者には、法定労働時間が厳格に適用され、変形労働時間制およびフレックスタイム制の適用禁止や残業や休日労働の禁止をして特別な保護をはかっております。
例外として、年少者のうち満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者(児童に該当しない者)は、非常災害の場合に、時間外(残業)や休日労働が可能となります。
(深夜業の制限)
第61条本文では「使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない」との規定があります。
(危険有害業務の制限)
第62条1項には「使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない」、同条2項では「使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない」とあります。
その他、条文中の厚生労働省令にあたる「年少者労働基準規則」では、年少者に就かせてはならない業務が詳細に挙げられています。
(坑内労働の制限)
第63条では「使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない」とあります。
(年少者の帰郷旅費)
第64条では「満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない」とあります。
(証明書の備え付け)
第57条1項では「使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」、同条2項「使用者は、前条第二項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない」とあります。
③年少者(16歳以上の男性)
第61条1項では「使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満十六才以上の男性については、この限りでない」とあります。
④児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者)
憲法第27条3項では、「児童は、これを酷使してはならない」という規定があり、それをうけて、労基法第56条では「使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない」とあります。就労させることができる「最低年齢」を定め、その年齢に達しないものを「児童」として、18歳未満の年少者と比べて、さらに特別な保護をはかっております。
ただし、下記の条件を満たせば、「児童」でも就労をさせることができます。
④a.13歳以上の児童
非工業的業種で、I.健康及び福祉に有害でないこと、Ⅱ.労働が軽易であること、Ⅲ.修学時間外に使用すること、Ⅳ.所轄労働基準監督署長の許可を得ること
Ⅲ.に関して、原則、修学時間と通算して、1日7時間、1週40時間が限度となります。
④b.13歳未満の児童
非工業的業種のうち「映画の製作又は演劇の事業」に限り、13歳以上の児童と同様、上記と同じⅠ~Ⅳの条件を満たせば、就労させることができます。
労基法上では成年擬制は適用されないので、例えば16歳の女性が婚姻をして成人とみなされても、労基法上の成人として扱われません。引き続き、年少者保護の各条文が適用されます。ただし、労働契約を締結する場面では成人として扱われるため、親権者の同意は不要となり、単独で有効に労働契約を締結することができます。
◆社会保険法
(健康保険)
雇用された未成年者(被用者)の勤務が、健康保険の加入条件を満たせば、加入となります。未成年者だから加入しない、成人だから加入するという基準ではありません。
「被扶養者」の立場で考えると、被扶養者となるかは被保険者(被用者)との親族関係性や収入の見込額によって決まるため、こちらも未成年者か否かは関係がありません。
(厚生年金)
厚生年金の加入条件は基本的に、健康保険と同じとなります。厚生年金の加入条件を満たす勤務であれば加入、未成年者か否かは関係がありません。また、厚生年金の加入者は、国民年金法(以下、国年法)の第2号被保険者となります(一部の例外があります)。国年法第7条1項2号では、その資格について、「厚生年金保険の被保険者」と規定されているだけで、年齢に関する条件(下限)はありません。
(国民年金)
国年法第7条1項1号では、第1号被保険者の資格について、「二十歳以上六十歳未満の者であって」とあります。現行の成年20歳と同じではありますが、「成年」「未成年」という基準、規定の仕方ではないので、必ずしも今回の民法改正と連動して、国民年金の加入開始年齢が引き下げられるわけではありません。
国年法第7条1項3号では、被用者の配偶者に関係する第3号被保険者の資格について、「二十歳以上六十歳未満のもの」とあります。第1号被保険者と同様、現行の成年20歳と同じではありますが、「成年」「未成年」という基準、規定の仕方ではないので、必ずしも今回の民法改正と連動して、加入の下限年齢の引き下げが行われるわけではありません。
また、未成年どうしが婚姻をして、夫婦の一方が厚生年金に加入し、他方を扶養する場合を考えると、成年擬制は年金制度に関係がないので、扶養される者が第3号被保険者とはなりません。20歳に達してはじめて、第3号被保険者となります。配偶者が20歳未満の場合、健康保険の被扶養者にはなるが、国民年金の第3号被保険者にはならないことに注意をしましょう。
◆税法・年末調整関係
社員の扶養親族に異動が生じた場合や年末調整を行う前には、社員から「扶養控除申告書」を提出してもらっていると思います。申告書において「年少扶養親族」や一部の「特定扶養親族」が未成年者に該当しますが、前者では「16歳未満」、後者では「19歳~23歳未満」と年齢が明確に定まっており、必ずしも現行の成年20歳を基準として連動しているわけではありません。
他方、源泉徴収票(受給者交付用、給与支払報告書の市区町村提出用、法定調書の税務署提出用)において、給与所得者本人(受給者)が未成年者の場合に「〇印」を付す欄があります。この未成年者は、民法上の未成年者を指しますので、成年擬制によって成年とみなされる場合は「〇印」を「付さない」ことになります。
◆民事訴訟法・労働審判法
昨今、労使の争いが公的機関に持ち込まれて解決することが多くなっております。必ずしも、いきなり裁判所による訴訟となるわけではありません。「あっせん」や「労働審判」を経て、その段階でも解決に至らない場合は訴訟となりえます。
「あっせん」や「労働審判」の詳細につきましては下記をご覧ください。
https://media.o-sr.co.jp/news/news-29817/#i-3
ここでは、訴訟の基本的なルールを定めた、訴訟法の一般法たる性格をもつ「民事訴訟法(以下、民訴法)」に関して、説明をしていきます。このルールは労働審判法にも「準用」されております。
キーワードとなる「(民訴法上の)訴訟能力」について、みていきましょう。
「訴訟能力」とは「訴訟当事者がみずから有効に訴訟行為をし,またこれを受領する能力」をいいます。「みずから有効に」訴訟行為ができる能力というと、民法における、単独で有効に法律行為ができる能力(=行為能力)と似ております。
民訴法第28条によると、訴訟能力は,民訴法に特別の定めのある場合を除き民法その他の法令に従うため、民法において完全な行為能力を有する者は、民訴法上、完全な訴訟能力も有していることになります。他方、「制限行為能力者」たる未成年者については、民訴法第31条本文では、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない」とあります。
労働審判においても、同様の考え方をします。労働審判法第29条が、非訟事件手続法第16条を準用し、その非訟事件手続法第16条が、民訴法第31条を準用しております。
2022年4月1日以降で変わるもの
変わるものとしては、民法上の「成年」規定と連動するものや、成年の引き下げと同じタイミングで法改正が行われるものがみられます。
➀18歳以上20歳未満の者の契約等の法律行為
2022年4月1日(以下、施行日)前は、18歳以上20歳未満は未成年者であるため、契約を締結する際には法定代理人の同意が必要となります。施行日以後は18歳以上が成年となるため、法定代理人の同意は不要で、単独で有効に契約を結ぶことができます。
ただし、単独で有効に契約が可能になるのと同時に、取消権といった保護もなくなり、自ら責任を負うことになるのを忘れてはいけません。
➁婚姻による成年擬制(民法第753条)
施行日から、男女ともに婚姻可能年齢が18歳となり、かつ、成年が18歳に引き下げられることによって、どちらの年齢も18歳となるため、成年とみなす必要性はなくなり、第753条は削除されます。
例外として、施行日時点で16歳以上(誕生日が2006年4月1日まで)の女性については、引き続き、18歳未満でも婚姻が可能で、その範囲において、限定的ではありますが、成年擬制が適用されることになります。
③民訴法上の訴訟能力
「訴訟能力」は民訴法第28条により、民法上の成年と連動しております。今回の改正民法施行に伴って、訴訟能力の下限を引き続き20歳に維持する特段の措置はないため、施行日以降は18歳以上の者が、完全な訴訟能力を有することになります。
④源泉徴収票の「未成年者」欄
施行日前では、婚姻していない20歳未満の給与所得者本人が未成年者に該当していました。施行日以後は、18歳未満(成年擬制が適用される一部の女性を除く)の者が該当することになります。
2022年4月1日以降も変わらないもの
民法の「成年」連動していないもの、法改正によって引き続き20歳に維持するものがみられます。
➀従前のもの
施行日前に18歳、19歳であった者が、法定代理人の同意を得ずに締結した契約については(施行後に18歳、19歳の者が成人となったとしても)引き続き、取り消しをすることができます。
➁飲酒、喫煙
成人が18歳以上になっても、連動して自動的に、飲酒や喫煙が18歳から可能になるとは限りません。禁止している法律が施行日以降にどうなるかを確認してみましょう。
各法律によれば施行日以降も、引き続き、20歳未満者の飲酒や喫煙は禁止されることになります。施行日前では「未成年者飲酒禁止法」「未成年者喫煙禁止法」だった法律名は、施行日以降は「二十歳未満者飲酒禁止法」「二十歳未満者喫煙禁止法」となります。
上記③~⑫は、施行日以降も引き続き、取り扱いや年齢に変更はありません。
人事・労務担当者への影響は?
◆労働基準法関係
施行日前後で違いが生じるのは「18歳以上20歳未満」の者となります。18歳未満の「年少者」や「児童」は引き続き、変更はありません。
労基法上、「未成年者」という文言は、第58条、第59条、第72条でみられます。
そのうち、58条1項と59条は実質的に変更がありません。どちらも未成年者が特別に行える旨を定めた規定であり、成人になっても行えることに変わりがありません。以下、条文を確認しましょう。
第58条1項「親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない」
第59条「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない」
ただし、第58条1項に関しては、民法によって労働契約には親権者による「同意」が必要となりますが、施行日以降、18歳以上の者は単独で有効に労働契約を締結することができるようになります。現行で、法定代理人の同意を証する同意書(を兼ねた書類)を運用している会社の人事・労務担当者にとっては、そのような書類が不要、または訂正が必要になる可能性がありますので注意をしましょう。
なお、施行日前時点の18歳以上20歳未満の者による労働契約は、施行日以後も引き続き、同意が必要となりますので、会社として同意がない場合の問題・リスクを回避するように心がけましょう。
さらに、18歳は学年でいうと、一般的には高校3年生となります。成年の基準は学年ではなく誕生日となりますので、同じ高校3年生でも時期によって成人と未成年者が混在します。そのため、契約の締結方法、時期、フロー等について再度、運用等を確認した方がいいかもしれません。今までは、高校3年生であれば全員未成年者として扱い、同意書をもらえばよかったところ、時期によっては、法的に同意が必要な方、不要な方の両方が発生するので、その辺を人事・労務担当者として留意をされた方がいいと考えます。
その他、第58条2項と第72条をみていきましょう。共通するのは、18歳以上20歳未満の者への手厚い「保護」がなくなってしまうことです。
第58条2項の「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる」について、施行日以降は、18歳以上20歳未満の者については、不利な場合の解除ができなくなります。
第72条の「第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と・・する」では、施行日前では、18歳以上20歳未満の者にも認められていた最低付与日数「12労働日」が、施行日以後では「10労働日」となり、手厚い保護がなくなります。
施行日以降も変更がない「年少者」「児童」については、民法上の未成年者と一致し、未成年者は、労基法上の「年少者」と「児童」の2種類に分けられることになります。また18歳以上の者は労基法上、成人と同じ業務や働き方ができていたので、施行日以降もその点変更はありませんが、民法上の成年と同じとなり、そういう意味ではスッキリします。
◆社会保険法関係
引き続き、変更はなく、手続き等で特段の影響はないと思われます。
◆税金・年末調整関係
税額に影響しない部分の変更となりますが、源泉徴収票の「未成年者」欄に注意が必要となります。施行日以後は、18歳未満の者に対して「〇」が付されることになります(婚姻した一部の女性には注意が必要です)。システムを使用している場合は、未成年者のフラグが法改正をしっかり反映されているかを確認し、正しい源泉徴収票が出力、作成できるようにしておきましょう。
◆民事訴訟法・労働審判法関係
「訴訟能力」は、民法上の成年と連動します。すなわち、成人であれば完全な「訴訟能力」を有することになりますので、施行日以降、18歳以上の者は単独で有効に提訴等の訴訟行為を行うことができます。労働審判でも同じように18歳以上の者が申立等の行為を有効に行うことができるようになります。
なお、民訴法31条のただし書きの「未成年者が独立して法律行為ができる場合」について、未成年者でも成人と同様の完全な訴訟能力を有し、単独で有効な訴訟行為ができると規定されております。
ここでいう「できる場合」については、労基法第58条1項の未成年者の契約、第59条の未成年者の賃金請求に関して、未成年者が単独で有効に訴訟が可能とする学説や裁判例がみられますが、他方、否定するものもあります。しかし、今回の改正で少なくとも18歳以上20歳未満の者については、完全な訴訟能力を有し、訴訟行為ができることになり、その部分の疑義は完全になくなることになります。準用される労働審判法も同様です。
まとめ
以上、施行日以降で「変わるもの」と「変わらないもの」を挙げ、取りまとめてきました。詳細を確認してみると、人事・労務担当者が関係しそうな領域(労基法、社会保険法、税金)では、それほど大きな影響はなく、法改正のインパクトが弱いと感じるかもしれません。18歳未満の者にいたっては引き続き、変更がありません。
だからといって安心して、何もしないのではなく、これを機会に18歳未満の未成年(年少者、児童)の取り扱いについて、再確認をしていただき、改めて誤りのない運用を心がけていただければと思います。熟知されている方におかれましても、いい復習ができたという感覚を持っていただければ、大変ありがたいです。
さらに、今回は、「成年」の考え方について、基本的、原理的な説明を交えてきました。人事・労務担当者にとっては、業務と直接関係しないこともあったかもしれませんが、その考え方は、業務外でも役に立ちますので、覚えていただけましたら、大変幸いと思います。
施行日の前後で、社会ではいろいろ混乱が生じるかもしれませんが、会社は社会の一員として、労基法の範囲に限らず、新たに成年となる18歳以上の方々のフォローが必要となるかもしれません。余裕を持って施行日を迎えることとしましょう。
筆者紹介
 社会保険労務士法人 HALZ(https://halz.co.jp/)
社会保険労務士法人 HALZ(https://halz.co.jp/)「外部人事部」をコンセプトに幅広い人事領域をサポートする社労士法人です。企業人事の実務経験、社労士として数々の企業様への労務コンサル経験をもとに、実務家目線に立ち企業様をサポート。