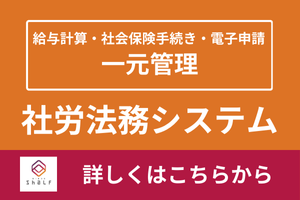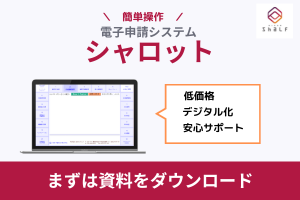【令和6年版】扶養控除(異動)申告書とは?出さないとどうなる?
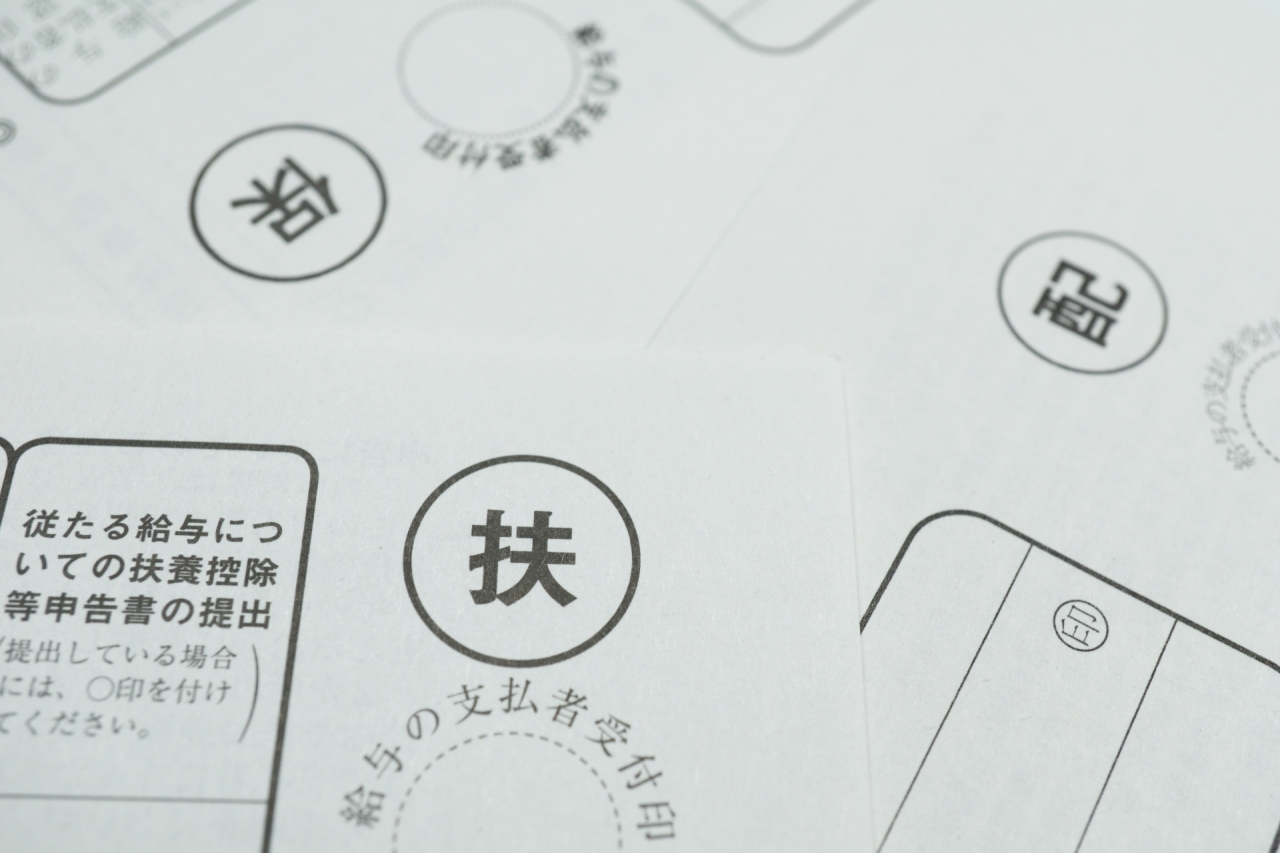
扶養控除申告書とは、簡単に言うと給与の支払いを受けている人が会社に提出する書類の事です。
扶養控除申告書は大切な書類ですが、提出しないとどうなってしまうのでしょうか。また、扶養控除申告書の正しい書き方はあるのでしょうか。
ここでは、扶養控除申告書に加えて、令和6年の年末調整のポイントとなる定額減税も合わせて詳しくご紹介します。
更新日:2024年10月2日
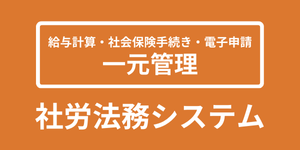
|
【目次】
|
扶養控除申告書とは?
扶養控除申告書を給与所得者が会社に提出すると、給与について、扶養控除を含めたいろいろな控除が受けられるのです。
扶養控除申告書を提出する目的は次の通りです。
所得税の扶養控除等の控除を受けられる
所得税は、扶養状況など個人的な生活状況を考慮し、所得控除として所得税の課税対象から除外する制度があるのです。
扶養控除申告書を給与所得者が会社に提出すると、会社は扶養控除申告書の扶養親族情報などをもとに必要な控除額を差し引き、毎月の所得税額を算出します。
年末調整時に必要となる
給与所得者は年末調整をするために以下のものを会社へ提出します。
- 配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための配偶者控除等申告書
- 生命保険や地震保険、社会保険
- 小規模企業共済掛金などの控除を受けるための保険料控除申告書
給与所得者がこれらを会社に提出した後、1年間の所得税額を算出します。そして、実際に徴収してある源泉徴収税額と比べて増減額を決め、その差額を年末調整で徴収したり還付したりします。
控除対象でなくても扶養控除申告書を提出する必要がある
給与所得者の中には、「所得税の控除項目に当てはまるものがないから提出がいらないのでは?」と考える人もいるでしょう。
しかし、控除対象でない場合でも、給与所得者は扶養控除申告書を会社に提出しなければなりません。
それは、扶養控除申告書の提出により、配偶者や親族、各種保険に関わる控除がないという点を会社が確認できるからです。
扶養控除申告書の根拠となる法律
扶養控除申告書は、所得税法と地方税法を基にして行われます。根拠となる法律は次の通りです。
- 所得税法第194条
- 所得税法施行令第316条の2
- 所得税法施行規則第73条、73条の2
- 所得税基本通達194~198共-3
- 地方税法第45条の3の2、第317条の3の2
- 地方税法施行規則第2条の3の2、第2条の3の3
先述の通り、扶養控除申告書は個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統一された様式になります。それは上記の地方税法に基づいたものです。
扶養控除申告書の提出期間
扶養控除申告書には提出期限があるので注意しましょう。扶養控除申告書は、その年に初めて給料を貰う日の前日までに勤務している会社に提出します。
新入社員・中途社員の場合
新入社員や中途社員の場合は、入社した会社で最初に給料を貰う日の前日までに扶養控除申告書を提出します。一般的には、入社時に提出を求められることが多いでしょう。
その他の社員の場合
たとえば、令和6年度の年末調整時には、来年分=令和7年度の扶養控除申告書が配られるのです。
では、どうしてまだ始まっていない来年分を提出しなければならないのでしょうか。
それは、年末調整時に扶養控除申告書を提出すると、令和7年度1月分の給料の計算時に間に合うからです。
そのため、来年分を提出する必要があります。
扶養控除申告書の書き方
年末調整は、扶養控除申告書を会社に提出している従業員全員について行われます。
しかし、給与の総額が2,000万円の人や、中途退職者で再就職の予定がある人、2か所以上から給与を受けている人で扶養控除申告書を自社以外に提出している人などは年末調整の対象になりません。
必要な扶養控除申告書を確認する
前年に回収した扶養控除申告書は当年の扶養控除で使用します。同じ用紙を年末に再び配布し、従業員に記入してもらうことで、変更があった場合の差額などを年末調整で調整するのです。
また翌年分は、翌年の毎月の給与計算の扶養控除額に使います。
その他、必要な申告書類
扶養控除申告書を提出する際、内容によっては添付書類を求められることがあります。
勤労学生の場合
勤労学生として所得控除を受ける場合、学校から交付される証明書を提示する必要があります。ただし、学校教育法によって設置された学校に通っている場合は不要です。国、地方公共団体などに準ずる一定の者により設置された専修学校や各種学校、職業訓練校などに通っている場合のみ、提示が求められます。すでに年末調整で勤労学生控除を受けている場合は、提示しなくも問題ありません。
障害者控除を受ける場合
障害者控除を受ける人が、非居住者の親族である場合は注意が必要です。送金関係書類、および親族関係書類を提示する必要があります。
送金関係書類とは、非居住者の親族に対して、給与所得者が送金した事実を証明する書類です。主に次のものを指します。
- 金融機関が発行した書類、またはその写し
- クレジットカード会社が発行した書類、またはその写し
親族関係書類については、次の項目で説明します。
参考:国税庁「No.1160 障害者控除」
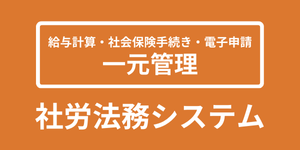
親族関係を証明する書類
障害者控除と同様に、扶養控除といった所得控除を受ける人が非居住者の親族である場合には、送金関係書類および親族関係書類を提出する必要があります。
親族関係を証明する書類とは、非居住者の親族が給与所得者の親族であることを証明するもので、以下のものをいいます。
- 日本国もしくは地方公共団体が発行した公的な書類、および非居住者親族のパスポートの写し。
- 戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など、外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(氏名、生年月日、住所または居所が確認できるものに限る)。
参考:国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」
住所地を確認する
扶養控除申告書の中で最初に確認するべきなのは、従業員本人の住所地です。
この住所地は、年末調整した翌年1月1日の住所になります。
引っ越したのに去年と同じ住所で扶養控除申告書を提出する場合が良くあるので、しっかり確認することが大切です。
扶養親族の年齢は年末時点
所得控除の対象になる扶養親族は、年齢要件がある場合があります。その場合、年齢によって以下のように控除額が変わります。
扶養控除申告書では、控除対象扶養親族や障害者の数、寡婦、勤労学生などの確認を行いましょう。申告する控除対象扶養親族や障害者などが、控除対象になるかどうかチェックすることが大切です。
扶養親族および控除対象扶養親族
扶養親族は、所得者と生計を一つにする人のことで、合計所得金額が48万円以下の人を指します。
- 親族(配偶者を除く)
- 児童福祉法の規定によって里親に委託された原則として18歳未満の児童
- 老人福祉法の規定によって養護受託者に委託された原則として65歳以上の人
控除対象扶養親族は、扶養親族の中で年齢が16歳以上の人を指します。
控除額はその年の分の合計所得金額から控除対象扶養親族一人につき38万円となります。
特定扶養親族
特定扶養親族は、控除対象扶養親族の中で年齢が19歳以上で23歳未満の人を指します。控除額はその年の分の合計所得金額から控除対象扶養親族一人につき63万円となります。
老人扶養親族
老人扶養親族は、控除対象扶養親族の中で年齢が70歳以上の人を指します。控除額はその年の分の合計所得金額から控除対象扶養親族一人につき48万円となります。
同居老親親族
同居老親親族は、老人扶養親族の中で以下のいずれも該当する人を指します。
- 所得者またはその配偶者の父母や祖父母
- 所得者または配偶者のいずれかと同居している人
控除額はその年の分の合計所得金額から控除対象扶養親族一人につき58万円となります。
障害者
障害者控除の金額は、障害者や特別障害者、同居特別障害者かによって控除額が変わります。
- 障害者:所得者本人や控除対象配偶者、扶養親族で、知的障害者更生相談所や児童相談所などで知的障害者と認められた人などを指します。
- 特別障害者:所得者本人や控除対象配偶者、扶養親族で精神上の障害によって弁識する能力を欠く状況に当たる人を指します。
- 同居特別障害者:特別障害者で所得者本人、所得者の配偶者またはその所得者と生計を一つにするその他の親族のいずれかと同居している人を指します。
これらの控除額は、障害者一人につき27万円、特別障害者一人につき40万円、同居特別障害者一人につき75万円となります。
寡婦、ひとり親控除
2020年分の年末調整・確定申告から「ひとり親控除」という所得控除が新設されました。
ひとり親控除の要件は下記のとおりです。
- 現状、結婚をしていない(または、配偶者がいても生死が不明)
- 合計所得金額が500万円以下である
- 総所得金額等が48万円以下の「生計を一にする子」がいる
勤労学生
勤労学生は、以下の1~4の全ての要件を満たす人の事です。
- 次のいずれかに該当すること:学校教育法に規定する学校の学生、生徒、児童、国や地方公共団体、私立学校法に規定する学校法人またはそれに準ずるものにより設立された専修学校・各種学校の学生、職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練学校の訓練生
- 自己の勤労に基づく所得があること
- 給与所得以外の所得後合計が10万円以下であること
- 合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)であること
控除額はその年の分の合計所得金額から27万円となります。
障害者の扶養親族欄は人数を記入する
障害者がいる場合、番号に〇をつけて内容を記載します。控除対象になるのは、本人と控除対象配偶者、扶養親族です。本人と控除対象配偶者の欄は〇だけをつけますが、扶養親族欄は〇をつけるだけでなく、人数も記載しましょう。
16歳未満の障害者は控除対象になる
また、障害者の扶養親族欄にも〇をつけて人数を記載します。さらに、障害者又は勤労学生の内容欄には、氏名と障害の状態、障害者手帳の種類や交付年月日についても記載します。
所得の見積額は控除後の所得を記入する
たとえば、給与所得(103万円)-給与所得控除(55万円)=給与所得(48万円)の場合、
配偶者の見積額が50万円の場合、50万円+65万円=115万円となるので、103万円を超えてしまい、配偶者控除から外れてしまいます。
配偶者特別控除
配偶者の年間所得は48万円以下でなければ配偶者控除を受けることができません。ですが、48万円を超える場合でも、配偶者の合計所得金額が48万円以上133万円以下の場合は、配偶者特別控除を受けられます。
年金受給者の場合の処理について
年金受給者については、公的年金控除(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)があるので、公的年金の収入のみの場合、65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下の人は控除対象になります。
また、遺族年金や障害年金は非課税になるので、所得見積額は0円と記載しましょう。
扶養控除申告書を出さないとどうなる?
では、従業員が扶養控除申告書を提出しないとどうなってしまうのでしょうか。ここからは、扶養控除申告書を出さないとどうなるのかをご紹介します。
毎月天引きされる税金が高くなる
給与所得の源泉徴収税額表の月額表は、甲欄と乙欄に分かれており、それぞれ天引きされる所得税の計算が異なるので注意しましょう。扶養控除申告書を提出していると甲欄、提出していないと乙欄となります。
必ず、甲欄で計算される税金<乙欄で計算される税金となるのです。
年末調整で税金が精算できなくなる
たとえば、1年間で源泉徴収した所得税が12万円で本来その年に負担するべき所得税が11万円だとすると、多く払いすぎている1万円が還付されます。
しかし、扶養控除申告書を提出しなければ、本来その年に負担するべき所得税が正しく計算できないのです。こうなると、自分で確定申告する必要が出てきます。
令和6年分の年末調整に関する注意点【定額減税】
今年の年末調整が例年と異なる点は、令和6年分所得税において、「定額減税」が実施されている点です。
定額減税とは
所得税において、定額による所得税額の特別控除をおこなうことで、
物価高から国民生活を守るため、デフレ脱却のための一時的な措置として、日本政府が実施している制度です。
対象者
- 令和6年分所得税の納税者である居住者
- 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(※))の者
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は2,015万円以下
控除額
| 定額減税額 | 所得税 | 個人住民税 |
|---|---|---|
| 本人分 | 3万円 | 1万円 |
| 同一生計配偶者又は扶養親族 | 1人につき3万円 | 1人につき1万円 |
そして年末調整時に年末調整時点の定額減税の額に基づき清算する年調減税事務を行います。
参照:国税庁「定額減税について」
扶養控除申告書の記載方法などについて詳しく知りたい場合は、国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」にもまとまった資料があるのでご参照ください。
転職したら扶養控除申告書の提出はどうなる?
たとえば、3月にA社を辞めて4月からB社に転職した場合、A社には昨年の年末調整時に提出しており、B社には4月入社時に提出しています。A社とB社のどちらの会社にも扶養控除申告書を提出していることになるのですが、同時期にA社とB社で働いているわけではないため、何も問題ありません。
A社で1月から3月までに貰った給与は、A社から貰った源泉徴収票に情報があります。この源泉徴収票をB社に出すと、B社でA社の給料も合算して年末調整してくれるのです。
年末調整を行う際には、転職する前に勤務していたA社の源泉徴収票を提出します。
まとめ
扶養控除申告書では、所得控除の対象になる扶養親族で対象になる親族が限定されています。また、年齢要件があり、年齢により控除額が変動するなどわかりにくい点がいろいろあるのでしっかり確認しておきましょう。
扶養控除申告書では、配偶者の有無など関係なく、会社から給料を貰っている人であれば、たとえ源泉控除対象配偶者や障害者に該当する同一生計配偶者及び扶養親族がいなくても、会社に提出してもらわなければならないのです。
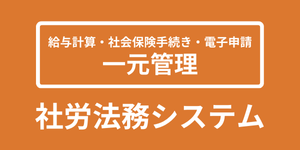
HR-GET編集部
![]() HR-Get(エイチアールゲット)は、創業から30年以上にわたり、社会保険労務士の方や、企業の労務ご担当者様向けにシステムを開発・提供・サポートをしている株式会社日本シャルフが運営するWEBメディアです。
HR-Get(エイチアールゲット)は、創業から30年以上にわたり、社会保険労務士の方や、企業の労務ご担当者様向けにシステムを開発・提供・サポートをしている株式会社日本シャルフが運営するWEBメディアです。
「人事、労務、手続き、働き方改革、トラブル」などに関するものをテーマとし、人事・労務に関わるビジネスに日々奮闘する、多忙な経営者や人事・労務の担当者に役立つ情報を提供します。