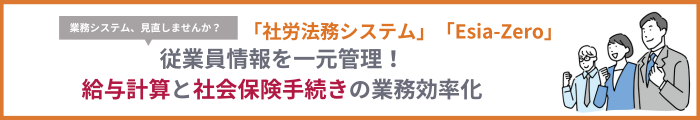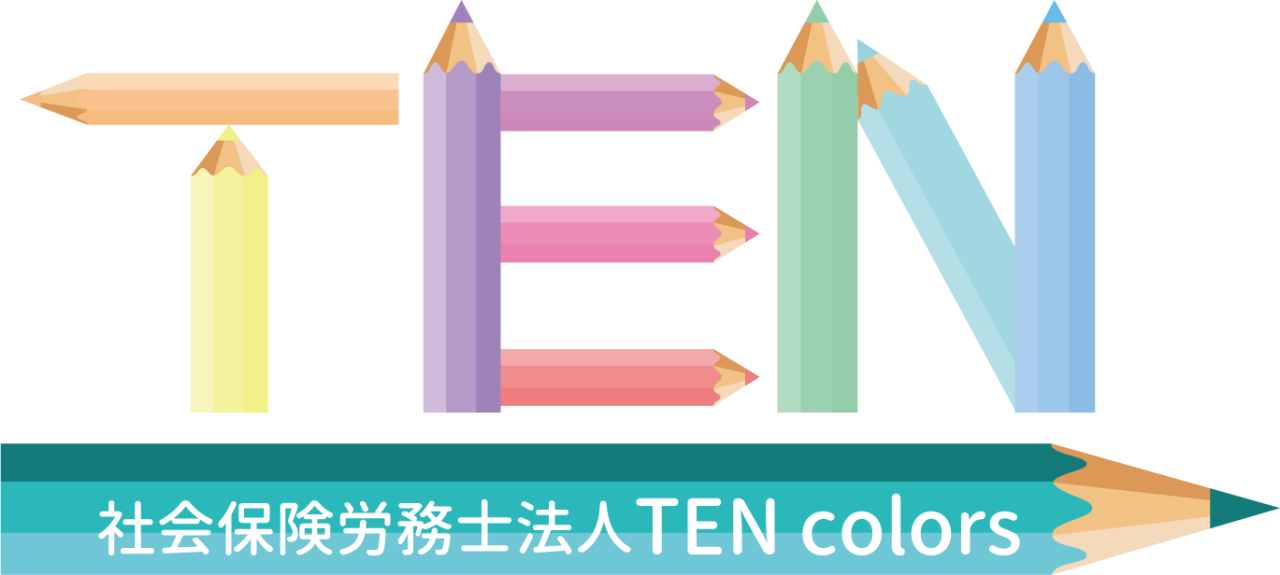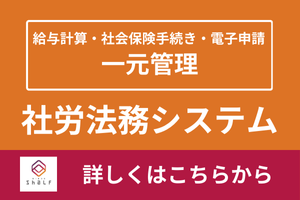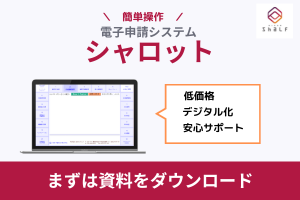【社労士に聞く】社会保険料の計算方法や金額、種類まで基本情報から分かりやすく解説!

社会保険料の仕組みや計算方法は従業員によっても異なるため複雑です。
ミスが許されないものですので、毎月頭を悩ませる労務担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、社会保険料の知っておきたい種類や計算方法、金額などについて詳しくご紹介します。
社会保険料について改めて確認し、業務の参考にしてくださいね。
|
【目次】
|
社会保険料とは
社会保険料を計算するためには、保険料率や標準報酬月額などの基礎知識が必要です。
それでは、社会保険料の種類について詳しくご紹介します。
社会保険料率について
社会保険料率は社会保険料を計算する際に使います。保険料率は保険の種類によって異なるため、保険ごとに確認する必要があります。また、保険料率は収支状況等をふまえて改定されることがあるため、最新の保険料率であるか確認することが必要です。
保険料額表
保険料額表では、保険料率のほか、保険料の計算に使う「標準報酬月額」とその等級、そして保険料がいくらになるのか確認できます。
一方、健康保険の保険料率は、健康保険組合ごとに異なります。会社の加入する健康保険組合で料額表を確認することになります。
また、協会けんぽ(全国健康保険協会)は、都道府県ごとにも料率が異なっています。保険証に記載の保険者の表記がどこの都道府県となっているかを確認し、協会けんぽのホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)で都道府県の表を確認しましょう。
保険料率の現状
以下の表で保険料率の現状をまとめました。【令和6年4月現在】
|
対象の保険 |
保険料率 |
備考 |
|
厚生年金 |
18.3%
|
今後引き上げられる予定はなし
会社と従業員で折半
|
|
健康保険 |
※10.0% |
※協会けんぽの平均保険料率
平成24年度から変更なし
会社と従業員で折半
|
|
介護保険 |
1.60% |
令和5年3月分(4月30日納付期限分)から |
|
雇用保険(一般の事業) |
1.55%
※詳細は厚生労働省雇用保険料率についてを参照
|
内訳は以下
・会社負担:0.95%
・従業員負担:0.60% |
|
労災保険 |
※各事業ごとの料率は厚生労働省令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)を参照 |
労災保険率、特別加入保険料率及び労務費率に変更あり |
標準報酬月額について
保険料の計算に使う金額が、「標準報酬月額」です。
保険料は、報酬や賞与に応じて算出されます。
会社から受ける基本給に、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた1カ月の総支給額(臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの)を「報酬月額」と言いますが、保険料の計算をより簡便化するために、「報酬月額」を一定の範囲に区分した「標準報酬月額」を使います。
「等級」といわれる金額の幅は、健康保険では1~50等級、厚生年金保険では1~32等級に区分されています。
なお、どの等級にあてはまるかは、事業主から提出された届書に基づき、日本年金機構が決定します。
標準報酬月額は、年に1度、見直される機会がありますが、昇給や降給により給与の金額が変わった場合は、随時、変更できる制度もあります。
保険料を適切に算出するためにも、給与額に変動があった場合は、変更の要件にあてはまるか確認しましょう。
標準報酬月額の決定するタイミング
標準報酬月額が決定するタイミングはいくつかあります。
-
資格取得時の決定
「資格取得時」とは、健康保険や厚生年金保険の被保険者となったタイミングのことをいいます。
入社した時や、労働時間が増えたことにより要件に該当した場合などがあります。
資格取得時では、現に受け取った報酬額ではなく、事業主との間で定められた額や報酬の支払い方法によって報酬月額の届出を行い、決定されます。
-
定時決定
定時決定は、毎年7月に実施されます。
これにより、報酬が極端に上がったり下がったりしない限り、4月から6月に支払われた報酬の平均額に基づき決定された標準報酬月額を1年間使用し、保険料の計算等を行うことになります。
ただし、給与の支給対象となった日数(支払基礎日数)が原則17日以上(※)の月を対象として平均額を計算します。
※特定適用事業所に勤務する短時間就労者は11日となります。
-
随時改定
随時改定は、昇給や降給、手当の金額に変更等があった場合に標準報酬月額を見直す制度です。
給与額の変動により、決定された標準報酬月額と実際に受け取る給与額が即さないことがあります。
実際に受け取る給与に応じた保険料を計算するためにも、変動があった時には随時改定の3要件を満たすかどうか確認しましょう。
②固定的賃金の変動した月以後、引き続く3月間に受けた報酬の平均月額と従来の標準報酬等級との間に2等級以上の差が生じたこと
③継続した3月間とも報酬支払基礎日数が17日以上(※)であること
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日となります。
-
産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した後に、育児等を理由に報酬が低下する場合があります。
このような場合、標準報酬月額の下がり幅が1等級であっても、標準報酬月額を改定することができる制度です。
産前産後休業の終了日の翌日(復帰した日)の属する月から3か月間の報酬で、標準報酬月額を改定します。
-
育児休業終了時改定
3歳未満の子を養育する従業員が育児休業を終了し、職場復帰した際に、報酬が休業に入る前の金額よりも低下することがあります。
このような場合、標準報酬月額の下がり幅が1等級であっても、標準報酬月額を改定することができる制度です。
育児休業の終了日の翌日(復帰した日)の属する月から3か月間の報酬に基づき、標準報酬月額を改定することができます。
等級について
健康保険では1等級(標準報酬月額58,000円)から50等級(標準報酬月額1,390,000円)まであり、厚生年金保険では、1等級(標準報酬月額88,000円)から32等級(標準報酬月額650,000円)まであります。
保険料は標準報酬月額に基づき算出されますので、等級が上がると保険料の額は大きくなり、等級が下がると保険料の額も少なくなります。
事業者や労務担当は労働者ごとの等級をしっかりと把握しておきましょう。
端数の対応について
また、雇用保険料を計算した際も端数が生じることがあります。
その場合、
2.保険料を現金で会社に支払う場合
個人負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
社会保険の種類について
健康保険
その会社によって保険者が異なりますし、保険料も異なります。
保険料率は、法律で上限(1,000分の130)と下限(1,000分の30)が決められており、それぞれの保険者がその範囲の中で保険料率を決め、運営しています。
また、40歳から64歳の被保険者は、介護保険料を支払います。
厚生年金保険
厚生年金保険は、一定の高齢になったときの老後の生活の安定を図るための老齢年金、病気やけがが原因で障害が残った際の保険加入者本人とその家族のための障害年金、さらに、保険加入者本人が不幸にも亡くなってしまった際の遺族のための遺族年金などの給付を行い、保険事故による生活の不安を救済する保険制度です。
厚生年金保険は公的年金制度のため、一定の基準を満たせば必ず加入することになります。
似ている制度として、厚生年金基金がありますが、こちらは私的年金制度のため、全ての企業が実施しているわけではなく、ニーズに合わせて加入する仕組みです。
また、厚生年金基金制度は、国の代わりに保険料の一部を集め、企業が独自に管理・運用し、給付を上積みすることができます。
介護保険
会社に勤めている場合、健康保険に加入している40歳から64歳の方が対象となります。
雇用保険
雇用保険は、労働者が働き続けられるように、また、働くことを促すため、失業者や60歳以上で会社勤めをしている一部の労働者、育児や介護休業をする労働者に給付するための保険料です。
労働時間週20時間以上で31日以上の雇用を満たす方は、雇用保険の対象になります。
ただし、以下に該当する場合は、原則として雇用保険の対象外となります。
- 個人事業主
- 家族従業員
- 法人役員
- 学生
労災保険
労災保険は、従業員が仕事中や通勤時に事故・災害にあった場合、会社が従業員やその遺族に補償すべきお金を肩代わりしてもらうために、会社が支払う保険料のことです。労災保険料は、個人の負担はありません。
労基法上の労働者にあたる方は、雇用期間や労働時間に関わらず、すべて補償の対象者になります。
また、原則補償対象外となる経営者も、特別加入のケースで対象になります。
社会保険料の計算方法
社会保険料は、報酬額に保険料率を乗じて計算します。
厚生年金保険の計算方法
従業員負担分=標準報酬月額×18.3%÷2
※厚生年金基金に加入しているときは、基金ごとに厚生年金基金の掛け金や厚生年金保険料率が違うので注意しましょう。
健康保険の計算方法
従業員負担分=標準報酬月額×保険料率(※加入する組合ごとに確認)÷2
介護保険の計算方法
従業員負担分=標準報酬月額×1.60%÷2
雇用保険の計算方法
従業員負担分=総支給額×被保険者負担分の保険料率
労災保険の計算方法
会社負担分=賃金総額×事業の種類に基づく保険料率
【まとめ】社会保険料の正しい知識を身に着け最大限の活用を
毎月の給与から引かれている社会保険料は、公助を要するさまざまな制度を支えています。
そんな社会保険料は、年齢や収入によって大きく異なります。
また、法改正などいろいろな要因によって加入対象や料率も変わるので注意が必要です。
社会保険料を毎月正しく計算するためには、被保険者の情報や法改正などの情報もしっかり集めておくことが大切です。
毎月の社会保険料の複雑な計算を効率化するには?
社労法務システムを利用すれば各事務所・従業員によって異なる毎月の社会保険料の計算を簡単におこなうことができます。
セットプランのほか、給与計算(キュール)のみ、社会保険労務手続き・電子申請(シャロット)のみの購入も可能です。
社労法務システムで社員情報、給与、申請業務、マイナンバーなど一元管理しながら、効率的に労務管理業務を行いませんか?
参考記事:社労法務システム+Esia-Zero(イージア・ゼロ)とは? 給与計算・社会保険手続きを一元管理できる労務システムを詳しく解説!
関連記事:基礎知識|雇用保険の加入条件、パートも可能?失業手当以外も網羅
筆者紹介
社会保険労務士法人TENcolors(https://sr-ten.com)